はじめに
経営者や責任者の方にとって、「なんとなく自分でやっている仕事」って、実はけっこう多いもの。
日々の業務に追われながら、
- 「これ、自分じゃなくてもいいのでは?」
- 「でも、どう判断すればいいかわからない…」
とモヤモヤしている方に向けて、
本記事では「手放すべき仕事の見極め方」と「外注する判断軸」についてお伝えします。
手放すべき仕事を見極める3つの視点
1. 「思考」を必要としない業務か?
手を動かせばできる業務は、外注しやすい代表格。
情報整理、転記、定型資料作成など、「考えるより処理する」業務は任せるべき領域です。
2. 1回の判断で10回の作業が減るか?
「これを外注すれば、何度も同じ作業をせずに済む」というものは優先的に外出しを検討。
月1回だけど2時間かかるような“重たいけど見落としがち”な業務にも注意。
3. 社内でしかできない仕事か?
文化的な前提や現場の判断が必要なもの以外は、整理・分解すれば外注できることも多いです。
「自分じゃなくていいかも」と思ったときにやるべき3つのこと
1. 業務を書き出す(まず見える化)
まずは、自分がやっているタスクを棚卸し。
日常の“ちょっとした作業”まで書き出してみることで、「これ、外でもいいかも」が見えてきます。
とはいえ、これを文章で書くのはけっこう面倒な作業です。
その場合は、SlackやLINEの録音メッセージを使って、業務を行ったタイミングで概要を音声で残しておくのも有効な方法です。
- 毎回スプレッドシートに手打ちするのは、忙しい方にとっては負荷が大きい
- 音声なら1タップで記録できる+後から秘書やスタッフがテキスト化も可能
この“音声メモ棚卸し”は、自分自身の業務の棚卸しにもなり、いわばレコーディングダイエットのような効果があります。
「無駄に感じていた業務が、実は自分の強みを発揮していた」
「逆に、誰でもできることを抱えていた」
という“気づき”につながることもあるので、まずは気軽に一度試してみるのもおすすめです。
2. 頻度と重さを評価する
毎日5分の業務も、月換算で2時間以上。
「頻度が高い」「時間がかかる」「精神的に負担」なものは、候補に挙げておくと◎
3. 誰に・どの粒度で任せるかを考える
「どこまで任せたいか?」を明確にすることで、社内か外注か、個人かサービスかの判断がスムーズになります。
外注に出す仕事の“成功パターン”と“失敗パターン”
成功しやすいパターン
- 成果物の基準が明確になっている
- 目的とゴールが共有されている
- フィードバック&改善サイクルがある
失敗しやすいパターン
- 「とりあえずお願いしてみた」丸投げ状態
- 頭の中にしかない業務を言語化していない
- 任せたけど“最終的に自分が直す前提”になっている
オンライン秘書はどこまで任せられるのか?
日常的な事務作業(メール整理/スケジュール調整/リサーチなど)から、
情報整理・Slack運用・会議設計といった“整える業務”まで、オンライン秘書が担える領域は広がっています。
実際にPress-tigeでは、
- タスク管理や業務フローの設計
- 情報共有のルール化
- 会議設計やSlack整理の伴走
- 「この内容で返しておきますね」といった提案型のチャット対応
など、単なる「作業代行」ではないサポートをご提供しています。
そして、Press-tigeの特長は、代表である私自身がキャッチアップに入り、状況・事業の理解を踏まえて秘書のディレクションを行う点にあります。
だからこそ、
- 「この内容って、こう伝えた方がいいですよね?」
- 「ここのSlack、仕組みごと整えましょうか?」
- 「この定例会議、目的を再設計しませんか?」
といった、“一歩先を見越した動き”も任せていただける関係性を築くことができます。
まとめ|「全部自分でやらないと」はもう終わりにしませんか?
“自分がやったほうが早い”を繰り返すほど、本質的な仕事から遠ざかってしまう。
仕事を「自分じゃなくていいもの」「今は自分でやるべきもの」に分ける視点を持つことで、
あなたの時間とエネルギーを“考える”ことに取り戻せます。
Press-tigeでは、業務整理から“任せ方の設計”まで、外注導入のパートナーとしてご相談いただけます。
▶︎ 無料相談はこちら

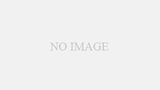
コメント