はじめに
「あの件は●●さんに聞かないと分からない」──そんな状況が常態化していませんか?
それは“頼れる人”がいるからではなく、“情報が整理されていない”から起きているのかもしれません。
本記事では、情報の属人化が起こる原因と、その解消に外注がどう役立つのかをご紹介します。
情報が属人化してしまう3つの理由
1. 情報が頭の中・個人PC・チャットに分散している
複数のツールや個人の記憶に情報が分散していると、「どこにあるか分からない」「本人が不在だと動けない」といった事態が起きやすくなります。
2. 業務がマニュアル化されておらず、暗黙知で回っている
教えるまでもない“なんとなくの対応”が実は組織を支えている場合も多く、それが属人化の温床に。
3. 業務内容を言語化できる人が限られている(=整理する時間もない)
忙しい人ほど「やったほうがいい」と分かっていても、情報整理に手が回らないというジレンマを抱えています。
属人化を解消する“外注”の使い方とは?
① 業務フローを“見える化”してもらう
情報が属人化している組織では、まず「誰が・いつ・何をやっているか」を一覧で可視化することが第一歩になります。
その際、オンライン秘書に:
- ヒアリング+チャットログなどをもとに業務を言語化してもらう
- 日次/週次の定型業務を棚卸しし、一覧にして見える化する
ただし、実際にその業務の一端にも触れずに“整理”をしようとすると、どうしても絵に描いた餅になりがちです。
たとえば:
- 表には見えない「部署横断の拾われないボール」
- 温度感で判断している調整業務
- 誰かが“なんとなく対応していた”非公式ルートの業務
こうした“整理されにくい現場”の実情まで把握するには、事務サポートなどの実務をオンライン秘書が一部でも担うことが、結果として業務整理の精度を大きく高めてくれます。
また、マニュアルの更新漏れも「中に入っていないと気づけない」典型例のひとつ。
日々の業務に触れているからこそ、「あれ、手順変わったのに反映されてないかも」といった細かな違和感にも気づきやすくなります。
② 社内のナレッジを集約する「まとめ役」を任せる
- Slackでよくある質問をFAQにする
- ドライブやNotionのフォルダ構成を整理
- 社内で“どこに何があるか”を整えて、探す時間をゼロに近づける
③ 誰かが辞めても回る“仕組み”を構築する
- 業務マニュアル・引き継ぎ資料の作成を秘書がサポート
- ルール・フロー・対応基準などを第三者視点で言語化
実際のオンライン秘書活用例
- 属人化していたSlackチャンネルを整えて、定型作業・タスク管理を整理
- 毎週の定例会で話している内容をログ化・フォルダ整理→社内全員が参照できるように
- 一人の社員が辞めても、業務が止まらなくなった(再構築のきっかけに)
まとめ|情報整理は「今すぐやるべき、後回しにされがちなこと」
属人化は、“放置しても気づかれない”けど、“放置し続けると止まる”問題です。
情報の整理・仕組み化は、内製でやるには負荷が高い。
Press-tigeでは、業務整理・ナレッジ集約・定型業務の見える化まで含めて、外から支える“整え役”として伴走しています。
▶︎ 無料相談はこちら

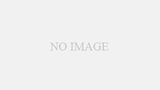
コメント