はじめに|「SVの役割って、どこまで?」と悩んでいませんか?
「加盟店からの連絡が全部本部に来る」「SVが本部判断をしてしまっている」──そんな状況、思い当たりませんか?
その背景には、“本部”と“SV”の役割の境界線が曖昧なことがあります。
本記事では、FC本部とSVの役割の違いと、その線引きを“仕組み”として整えるための考え方をご紹介します。
1. FC本部とSVの“役割の本質”は違う
本部の役割は、「戦略とブランド」を設計すること
- 事業戦略の設計
- ブランドの一貫性管理
- オーナー制度や契約条件の整備
SVの役割は、「現場との信頼構築と浸透」
- 日々の定例支援・相談対応
- 現場での方針の実行サポート
- オーナーの心理的なケア
本部=方針をつくる/SV=実行と支援を担う
この構造理解がないまま、「どこまで対応するか?」を話し合っても、ズレやすくなります。
2. 境界線が曖昧な本部でよく起きる問題
- オーナーからの問い合わせが「誰に言えばいいのか分からない」状態に
- SVが本部判断まで担ってしまい、責任が曖昧に
- 本部が駆け込み寺化し、施策や拡大業務が止まってしまう
結果的に、「SVが疲弊する」「本部が火消しに追われる」「信頼が個人ベースになる」といった事態に。
3. SV業務を線引きするための3つの軸
① 判断権限の線引き
「これはSV判断でOK」「これは必ず本部判断を仰ぐ」
この判断の“例外”を減らすことが、仕組みの第一歩です。
② タッチ領域の整理
SVが対応する内容を「定例支援/日常の相談/緊急対応」と分類し、それぞれに基準を設けることで負荷とブレを減らせます。
③ 情報共有のルール化
どの記録を、どこに、どのタイミングで残すか?
Slack/Notion/報告フォーマットなどに、標準ルールを定めておくと属人化が防げます。
4. Press-tigeが支援する「SV機能設計」とは
- SVと本部の役割と対応範囲の言語化(役割定義書)
- 加盟店との支援ステップの可視化(定例・チェックリスト)
- 支援ログと共有フォーマットの整備(記録の共通化)
「どこまでが誰の仕事か」を明文化し、SVの動きに再現性を持たせる。
それが本部として支援体制を整える第一歩になります。
まとめ|「どこまで任せるか?」より「どう仕組みに落とすか」が重要
境界線のモヤモヤは、“仕組みの不在”から生まれます。
Press-tigeでは、FC本部とSVの役割を「言葉とフォーマット」で整理し、支援体制をしくみに変える支援を行っています。
▶︎ 無料相談はこちら

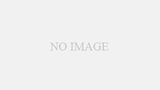
コメント